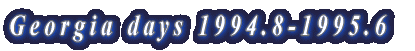
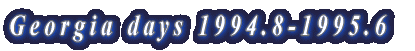
| エピソード Vol.1 「アメリカ留学に憧れたきっかけ」 |
| 幼い頃から外国に憧れ、小学校1年生頃、「将来は英語とフランス語を話せるようになりたい」と根拠もなしに思っていた。なぜフランス語だったのかは分からない。でも僕は自分の直感を信じ、道を選んでいた。14歳の時、日本全国の中学生たちとカリフォルニアに2週間の研修旅行に参加した。そこで僕は完全にアメリカナイズされてしまった。僕のグループリーダーだった横田先生は、熊本在住で幼稚園の園長先生をしている、尊敬すべき女性だった。ご主人はキリスト教の牧師さんだった。横田先生の3人お子さんは日本の中学を卒業し、高校から大学までアメリカで学んでいるという話を聞き、僕は「留学」というものにただならぬ熱意を持ち始めた。毎日毎日、先生に留学の話を伺い、僕も中学を卒業したらアメリカに留学したいと真剣に思った。帰国し、両親に会うなり即その希望を話すと、腰を抜かしたように驚き、即答は出来ないと言われた。僕たち親子はその日から、戦争の如く戦いが始まった。僕は何が何でも留学がしたい。しかし、両親は簡単にそれを受け入れられない。来る日も来る日も、親の顔を見るなり僕は留学の話をする。喧嘩になることもしばしばだった。留学に関する分厚い本を購入し、暗記するほどそれを毎日読み耽り、熊本の横田先生に電話をしては「両親を説得して下さい」とお願いした。一日中アメリカのことを想っていた。素晴らしい友人に巡り会えたあの奇跡のような2週間。憧れていたアメリカを直に体験し、僕は必ずあの場所に戻る、あの国こそが自分の居場所だと思った。 人と違うことをしてはいけない、レールを外れてはいけない。皆と同じことをしなさい。なぜ出来ないんだ。なぜしないんだ。突飛でもないことをするんじゃない。目立つことをするんじゃない。僕は、そんな日本の教育に疑問を感じ、違和感を覚え、次第に「嫌い」という感情になっていきそうだった。個性を潰す教育。なぜ、人と違っていけないのか。自分には合わない空気。そして合わない国。僕はアメリカに行きたい。それがすべてだと信じた。 そもそも、2週間のアメリカ研修旅行に参加すると言った時も、学校側は大反対だった。中学2年の3学期の始業式で、教頭先生が「春休みに日本全国の中学生がアメリカのカリフォルニアに2週間研修旅行に行くという企画がある」と発表したのを聞いた時、僕の心はざわついた。常々、そういう類のものに参加をしたくて、雑誌に載っている記事を両親に見せると「そういうんじゃなくて、学校が紹介してくれるようなものなら行ってもいい」と言っていたので、これなら行けると思い、両親に話を持ちかけた。以前から言っていた通り、「学校が紹介したのなら、安全な団体だろうから、どうしても行きたいというのなら行ってもいい」と承諾してくれた。僕は早速、教頭先生に詳しい話を聞きに行った。すると、予想外にも反対された。 「まだ学校の誰も、外国には行ったことがない。君のクラスメイトだって、更には先輩だって行ったことがない。それなのに、君ひとりが外国に行ったらどうなる?“あいつばっかり!”って羨望の眼差しだ。帰国してからが厄介なことになる。ひとりだけ外れたことをしてはいけない。そういうのに興味があるのなら、アメリカに行くのではなくて、地元にいるAET(英語圏から来た英語の先生)たちとの交流会に参加すればいいじゃないか」 自分で紹介したくせに、行きたいとなると反対するというのがどうにも理解出来なかった。担任も反対していた。1992年のことである。 職員室には何度か呼び出された。その団体が主催する研修旅行には、同じ市内の中学校から前年度に参加している生徒がいた。調べてみるから待てと言われていたが、僕は自分で資料を取り寄せ、申込書を送付した。 「待ちなさいと言ったのに、なぜ勝手に申し込んだのだ!」 教頭先生と担任から叱られた。学年主任は呆れ顔だった。そして、父親が学校に呼ばれた。父、教頭先生、担任、そして校長先生を交えての話し合いだった。教頭先生が先陣を切って反対する中、校長先生は言った。 「本人は行きたい、ご両親も行かせたい。一体、何の問題があるんでしょう?」 校長先生のその一言で、いとも簡単にあっさりと、僕のアメリカ研修旅行への参加は認められた。大反対を通していた教頭先生はだんまりを通していたという。 もうお亡くなりになってしまったが、僕はその校長先生を入学した時から、学校の中で一番尊敬していた。常に生徒を人間として扱い、生徒の目線で話をしてくれる素晴らしい先生だった。 「去年、他の中学校からこの研修旅行に参加した生徒がいる。その学校の先生のことは私もよく知っていて、電話をして聞いてみたんだ。そしたら、素晴らしい経験をさせてくれる団体だから、何も心配することはないと言ってたよ。楽しんでいらっしゃい」 校長先生は、僕のために時間を割き、簡単な英会話の手ほどき、また心構えをお話して下さった。先生がそこまでしてくれるのには、ひとつ理由があった。元々は英語教師だった校長先生は、若い頃から外国への憧れが強かった。英語の先生になれば外国に行けるという思いから、英語教師になったとお話されていたのを僕はずっと覚えていた。ご自分の娘さんも留学経験があるとのことだった。先生は、自らの想いや経験から、僕の気持ちをよく理解して下さったのだと思う。 「若いうちに外を見るのは大変貴重で素晴らしい経験です」 とても優しい眼差しで、そして力強く僕を励まし、心からそれが僕にとっていい勉強、いい経験になるよう願って下さっていた。学校の中で、どの先生よりも好奇心が旺盛で、生徒の視点から生徒を人間として理解する、という方だった。 あの校長先生でなかったら、僕はアメリカに行っていなかっただろう。そして、一緒に参加した全国の友人たちにも、熊本の横田先生にも出会うことはなかっただろう。 帰国してからは、僕の留学への想いが日を追うごとに増していった。両親は、「なぜアメリカに行きたいのか」と、その目的を僕に問うてきた。僕はあらゆる言葉で、目的を“作り”あげた。でも本音のところは、アメリカに対するただならぬ憧れ、日本の教育や日本文化への嫌悪、それだけだった。 「日本の高校は卒業して欲しい。そうしたら、アメリカの大学に行こうが、どこに行っても構わない。だから、せめて高校は日本にして欲しい」 と言う両親の提案を受け入れることは出来なかった。 学校側にも僕の希望は伝えていた。春が過ぎ、夏が来て、両親は熊本の横田先生にお会いする決意を固めた。 「ここに居ても留学に関して何の知識もなければ情報もない。実際に横田先生にお話を伺いたい」 横田先生に電話を入れると、「ここは九州の熊本ですよ!」と驚いた。 「8月に用事があって東京に行きます。そこなら高橋さんにとっても便がいいでしょう。その時、お会いしませんか」 先生はそんな提案をして下さった。僕の留学が実現する一歩となる会合、やっと留学に向けて動き出したと思った。 しかし、追い風だと思っていた風はくるりと向きを変え、僕をアメリカには行かせまいとする何かがうごめいていた。 エピソード Vol.2 へ |